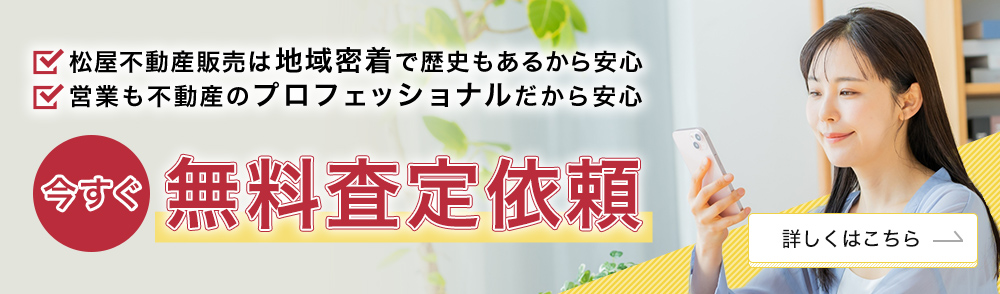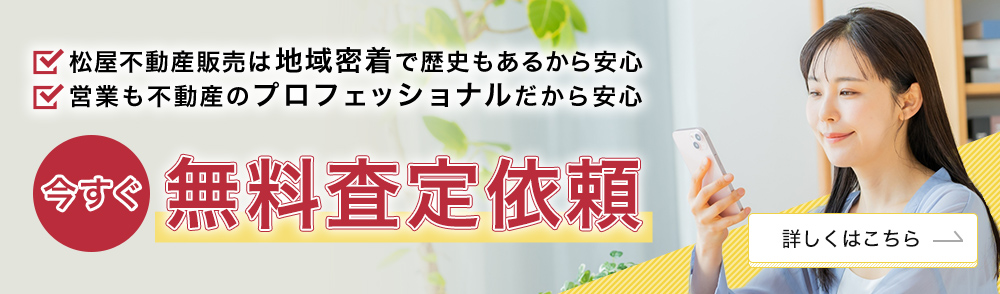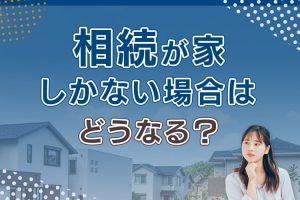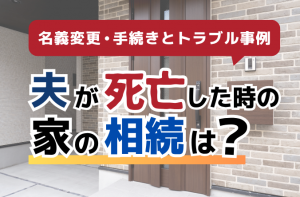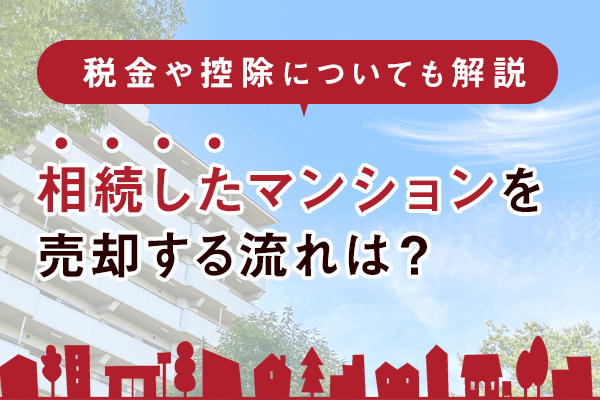
「親のマンションを相続したけど、どうすればいいのかわからない」
「できるだけ早く売却したいけど、手続きや税金面が不安」
このようなお悩みをお持ちの方は多いのではないでしょうか。
相続不動産の売却は通常の不動産売買とは異なり、相続登記や税の申告、特例制度の活用など、複雑な手続きが発生します。
適切な手順を知らないまま進めてしまうと、相続人同士のトラブルや不要な税金の支払いといった、思わぬリスクに直面するおそれがあります。
本記事では、相続したマンションを売却する前に必要な準備や売却の流れ、注意すべき税金・費用、そして活用できる特例制度までを具体的に解説します。
相続したマンションの売却を検討している方はぜひ参考にしてください。
- 相続したマンションを売却する前の準備について
- 相続したマンションを売却する流れ
- 相続したマンションを売却する際の税金

監修者
松屋不動産販売株式会社
代表取締役 佐伯 慶智
住宅・不動産業界での豊富な経験を活かし、令和2年10月より 松屋不動産販売株式会社 にて活躍中。それ以前は、ナショナル住宅産業(現:パナソニックホームズ)で8年間、住友不動産販売で17年間(営業10年、管理職7年)従事。
目次
相続したマンションを売却する前にすること
相続したマンションを売却するには、売却の準備として以下の手続きを行う必要があります。
- 遺言書があるかどうかをまず確認する
- 相続登記を行い、マンションの名義を相続人に移転する
- 相続税が発生する場合は申告と納税を行う
上記の手続きを怠ると、手続きが遅れたり税金トラブルが起きたりするため注意が必要です。
事前に把握しておくことで、売却手続きがスムーズになり、トラブルを未然に防ぐことができます。
それぞれの手続きについて順番に解説します。
遺言書の有無を確認する
被相続人が亡くなったら、最初に行うべきことは「遺言書が残されているかどうかの確認」です。
遺言書がある場合、その内容に沿ってマンションの相続手続きをスムーズに進めることができるため、相続人間の無用な争いやトラブルを未然に防ぐことができます。
遺言書には大きく分けて「公正証書遺言」と「自筆証書遺言」があります。
公正証書遺言の場合はすぐに手続きに移れますが、自筆証書遺言の場合は家庭裁判所で「検認」という手続きを経なければ開封できません。
検認を行わずに遺言書を開封すると罰則があるため注意しましょう。
不明瞭な内容や複数の遺言書が見つかった際は、弁護士や司法書士などの専門家に相談すると安心です。
遺言書がない場合は遺産分割協議を行う
遺言書が見つからない場合や作成されていなかった場合は、法定相続人全員が参加する「遺産分割協議」を行い、誰がマンションを相続するかを決める必要があります。
協議で合意に至った場合、その内容をまとめた「遺産分割協議書」を作成し、相続人全員が署名し実印で押印します。
遺産分割協議書がないと相続登記を進めることができず、売却も行えません。
協議がまとまらない場合、売却時期が遅れたり、最悪の場合には家庭裁判所での調停や審判となり時間がかかります。
スムーズな協議のためにも、話し合いが難しい場合には第三者の専門家を交えることを検討しましょう。
所有権を被相続人から相続人へ移転するために相続登記をする
マンションを誰が相続するかが確定したら、次に法務局で「相続登記」を行います。
相続登記とは、不動産の所有権を被相続人(亡くなった人)から相続人へと正式に変更するための手続きです。
登記を行わないと第三者への売却は認められず、取引が成立しないため注意が必要です。
相続登記の手続きでは、主に以下の書類が必要になります。
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本・改正原戸籍
- 相続人全員の戸籍謄本
- 相続人全員の印鑑証明書
- 遺産分割協議書
- 固定資産税明細書
- 不動産の登記事項証明書
- 相続人のうち新たな所有者の住民票
また、登録免許税という費用も発生します。
なお、2024年4月からは相続登記が義務化され、正当な理由なく手続きを行わない場合は過料が科されるため、忘れずに手続きを進めましょう。
相続財産の総額が基礎控除額を超える場合は相続税の申告をする
相続財産が基礎控除額(3,000万円+法定相続人の数×600万円)を超える場合、相続税の申告および納税が必要となります。
不動産は評価額が高くなることも多いため、手持ちの現金が少なくても相続税の対象になる可能性があります。
特に都心部のマンションなど、価値が高い不動産では注意が必要です。
相続税の申告期限は被相続人が亡くなった日から10ヶ月以内と決められており、期限を過ぎると延滞税や無申告加算税などが課される可能性があります。
不動産を売却する予定の場合、その譲渡益によって税額が変動することもあるため、早めに税理士へ相談し、資金計画を立てておくと安心です。
参考:【相続税の申告要否判定コーナー】-相続税の申告が必要となる場合|国税庁
相続したマンションを売却する流れ
相続手続きが完了したら、次はマンションの売却を進めます。
以下に示すステップを順に踏むことで、売却をスムーズに進められます。
- 複数の不動産仲介業者にマンションの査定を依頼する
- 査定結果をもとに不動産仲介業者と媒介契約を締結する
- 不動産仲介業者がマンションの広告・宣伝を行う
- マンションの買主と売買契約を締結する
- マンションの引き渡しと代金の受け取りをする
- 譲渡所得が発生した場合、確定申告を行う
各段階では判断や手続きのポイントがあるため、全体の流れを把握しておくことがとても重要です。
順番に解説します。
複数の不動産仲介業者にマンションの査定を依頼する
マンションを売却する際の第一歩は、物件の適正な売却価格を把握することです。
不動産の価格は立地や築年数、周辺環境、管理状況など多くの要素に左右されるため、まずは複数の仲介業者に査定を依頼することをおすすめします。
複数の査定結果を比較することで、相場感がつかめるだけでなく、業者ごとの対応力や知識レベル、提案の内容も確認でき、信頼できるパートナー選びの判断材料になります。
査定方法には「机上査定」と「訪問査定」の2種類があります。
机上査定は物件情報や周辺データをもとに短時間で算出される簡易的な方法で、目安価格を知るのに便利です。
一方、訪問査定は実際に現地を確認し、物件の状態や日当たり、眺望、騒音なども加味してより精度の高い査定を行います。
金額の高さだけで業者を決めるのではなく、査定価格の根拠や売却戦略の具体性も含めて総合的に判断しましょう。
査定結果をもとに不動産仲介業者と媒介契約を締結する
複数社の査定結果を比較したら、最も信頼できる業者を選定し「媒介契約」を締結します。
媒介契約とは、売主が仲介業者に売却の仲介を正式に依頼する契約で、「一般媒介」「専任媒介」「専属専任媒介」の3つの形式があります。
| 項目 | 一般媒介契約 | 専任媒介契約 | 専属専任媒介契約 |
|---|---|---|---|
| 他業者への仲介依頼 | 可能 | 不可 | 不可 |
| 自己発見取引(自分で入居者を見つけた場合の直接契約) | 可能 | 可能 | 不可 |
| 募集状況の報告 | なし | 2週間に1回以上 | 1週間に1回以上 |
| レインズへの登録期限 | 登録義務なし | 契約締結後7営業日以内 | 契約締結後5営業日以内 |
| 契約期間の上限 | 制限なし | 3ヶ月以内 | 3ヶ月以内 |
媒介契約の種類によって、依頼できる業者数や報告義務、自己発見取引の可否などが異なりますので、自分に合った契約形態を選ぶことが重要です。
例えば、じっくり時間をかけて売却したい方は複数業者に依頼できる「一般媒介」、一社と密に連携しながらスピード感を持って売却したい方には「専任媒介」や「専属専任媒介」が向いています。
契約の際には、広告の出稿範囲や販売価格の設定、仲介手数料、契約期間などについても確認し、納得のいく内容で契約を進めましょう。
不動産仲介業者がマンションの広告・宣伝を行う
媒介契約を結ぶと、選定した仲介業者がマンションの販売活動を本格的に開始します。
主な広告手段には、SUUMOやアットホームなどの大手不動産ポータルサイト、自社ホームページ、折込チラシ、店頭掲示などがあり、できるだけ多くの人に物件の存在を知ってもらうための工夫が必要です。
業者によってはプロのカメラマンによる写真撮影や、インテリアの演出(ホームステージング)を提案してくれるところもあります。
また、広告の質は成約率に直結します。
特に物件写真やキャッチコピーは、閲覧者の興味を引く大切なポイントです。
間取り図の見やすさや周辺施設の情報、交通アクセスのアピールなど、購入希望者が「実際の生活」をイメージしやすい情報提供を心がけましょう。
なお、販売活動が始まった後も、どのような反響があるかを定期的に確認し、価格の見直しや広告内容の修正など柔軟に対応することも大切です。
マンションの買主と売買契約を締結する
内覧や条件交渉を経て買主が決定したら、売買契約の締結に進みます。
売買契約書には、売買価格、引渡時期、支払い方法、契約解除に関する条件など、今後の取引に関わる重要な内容が詳細に記載されます。
契約の際には売主・買主の双方が契約内容をしっかり確認し、納得したうえで署名・押印を行いましょう。
また契約時には、宅地建物取引士による「重要事項説明」が行われます。
これは、買主に対して対象物件の法的な権利関係や制限事項、インフラ設備の整備状況などについて説明するものです。
契約後は、通常、買主から手付金(売買価格の5〜10%程度)が支払われ、正式な契約成立となります。
マンションの引き渡しと代金の受け取りをする
売買契約が無事に成立したら、次は「決済・引渡し」に向けて準備を整えます。
決済・引渡し日当日に買主から残代金が支払われ、司法書士が立ち会って所有権移転登記の手続きを行います。
登記が完了したら鍵の引き渡しを行い、マンションの売却手続きは完了です。
引渡し前には、室内の最終清掃や家具・家電の撤去、付帯設備の点検などを済ませておく必要があります。
エアコンや給湯器などの設備が故障している場合、そのまま引き渡すとトラブルに発展する可能性もあります。
買主に気持ちよく入居してもらえるよう、丁寧で誠実な対応を心がけましょう。
譲渡所得が発生した場合確定申告を行う
マンションの売却によって譲渡所得が発生した場合、翌年の確定申告が必要です。
譲渡所得は「売却価格-取得費-譲渡費用」により計算され、個人名義の場合は所有期間が5年を超えるか否かで税率も異なります。
取得費には購入時の代金だけでなく、仲介手数料や登記費用、リフォーム費用なども含まれますが、領収書などの証明資料が必要になるため予め準備しておきましょう。
相続で取得した不動産には「取得費加算の特例」「居住用財産の3,000万円特別控除」「空き家特例」など、税負担を軽減できる制度があります。
ただし、適用には細かな要件があり、適用の可否や書類の準備に専門的な知識が求められるため、税理士への相談をおすすめします。
誤って申告を怠った場合、追徴課税の対象になることもあるため、早めの準備が安心です。
相続したマンションを売却する際の税金
相続したマンションを売却する際には、いくつかの税金が関係します。
特に代表的な税金が以下の2つです。
- 印紙税
- 登録免許税
それぞれの特徴について順番に解説します。
印紙税|不動産売買契約書に貼付する収入印紙にかかる税金
マンションを売却する際に作成する「不動産売買契約書」には、印紙税法に基づき収入印紙を貼付する必要があります。
これは文書1通ごとに発生する税金で、契約金額に応じて金額が決まっており、例えば1,000万円超~5,000万円以下の取引であれば1万円の印紙が必要です(2024年現在、軽減措置あり)。
契約書に印紙を貼付し、消印(割印)をしなければ納税が完了していないと見なされ、過怠税が課されることがあります。
通常、契約書は売主・買主双方で1通ずつ作成されるため、印紙税も2倍かかる点に注意が必要です。
印紙代の負担割合は事前に取り決めておくのが一般的で、慣例としては折半することが多く見られます。
参考:印紙税額の一覧表|国税庁
登録免許税|所有権移転登記を行う際に発生する税金
相続したマンションを売却するためには、まず被相続人から相続人への相続登記を行い、さらに売却時には買主へ所有権を移転する登記を実施する必要があります。
その際に発生するのが「登録免許税」です。
登録免許税は不動産の登記を法務局で申請する際に課税され、課税標準(固定資産税評価額)に一定の税率をかけて計算されます。
相続登記にかかる登録免許税の税率は0.4%、売却による所有権移転登記では通常2.0%となっており、金額によっては数万円から十数万円に及ぶこともあります。
また、登録免許税に加えて、登記申請を司法書士に依頼する場合は報酬も発生します。
費用面の見積もりを事前に確認し、手元資金に余裕を持たせておくと安心です。
相続したマンションを売却することで利用できる特例
相続したマンションを売却する際に、活用できる主な3つの特例は以下のとおりです。
- 居住用財産の3,000万円特別控除
- 取得費加算の特例
条件を満たせば、譲渡所得から一定額を差し引ける税制上の特例がいくつか用意されています。
ここでは、それぞれの特例について解説していきます。
居住用財産の3,000万円特別控除
「居住用財産の3,000万円特別控除」とは、相続人が実際に居住していたマンションを売却する場合、譲渡所得から最大3,000万円までを控除できる制度です。
自宅として使用していた不動産を売る際に利用でき、課税対象額を大きく減らせるため、非常に大きな節税効果があります。
この特例を適用するには、売却時点まで相続人自身がそのマンションに居住していたことが必要です。
相続後にすぐ賃貸に出したり、空き家のままだった場合は適用されない可能性があります。
また、過去に居住用財産の3,000万円特別控除を使ったことがある場合は再適用できません。
申告の際には適用要件を満たす証拠書類(住民票など)を整えることも重要です。
取得費加算の特例
「取得費加算の特例」は、相続によって取得した不動産を相続税の申告期限から3年以内に売却した場合、支払った相続税の一部を不動産の取得費に加算できる制度です。
譲渡所得を圧縮できるため、課税対象額が減り、結果として税負担を軽減する効果があります。
ただし、加算できるのは売却した物件に対応する相続税部分のみで、すべてを加算できるわけではありません。
適用期限が過ぎるとこの特例は使えなくなるため、売却のタイミングには注意が必要です。
相続税申告を行った人に限定される制度でもあるため、該当するかどうかを税理士に確認し、計画的な売却と申告を行いましょう。
相続したマンションを売却するなら松屋不動産販売
相続したマンションの売却には、相続登記・税務申告・価格査定・契約手続きなど、多くの専門知識が求められます。
初めての方にとっては不安も多く、誰に相談すればよいか迷ってしまうことも多いです。
松屋不動産販売では、相続不動産の売却実績が豊富なスタッフが在籍しており、相続開始から売却完了までをトータルでサポートいたします。
地元密着のネットワークと丁寧な対応で、ご家族の思いを尊重しながらスムーズな売却を実現します。
ご相談は無料ですので、ぜひお気軽にお問い合わせください。
相続したマンションの売却に関する質問
相続したマンションを売却するにあたって、売却のタイミングや確定申告の準備、生前贈与との違いなど、よくある疑問点がいくつかあります。
ここでは、特に質問の多い3つのテーマについて簡潔に解説します。
- 相続したマンションを3年以内に売却するとどうなる?
- 相続したマンションを売却して確定申告をするには何が必要?
- マンションを生前贈与と相続ではどちらが得?
事前に疑問を解消しておくことで、安心して手続きを進められます。
それぞれの詳細は以下をご覧ください。
相続したマンションを3年以内に売却するとどうなる?
相続したマンションを、相続税の申告期限(死亡から10か月)から3年以内に売却した場合、「取得費加算の特例」が適用される可能性があります。
これは支払った相続税の一部を取得費に加算できる制度で、譲渡所得を圧縮できるため、節税効果が期待できます。
この特例を受けることで、譲渡所得税・住民税の負担が軽くなる場合があります。
適用には相続税の申告がされていることが前提のため、該当するかどうかは税理士などの専門家に確認するのが安心です。
条件を満たしていれば、できるだけ早めの売却を検討しましょう。
相続したマンションを売却して確定申告をするには何が必要ですか?
相続したマンションを売却して譲渡所得が発生した場合、翌年に確定申告を行う必要があります。
必要な書類には、「売買契約書」「仲介手数料の領収書」「登記費用の明細」「取得費の証明書類(売買契約書やリフォーム費用明細)」「相続税申告書の写し」などが挙げられます。
また、特例の適用を受ける場合には、要件を満たすことを証明する書類(住民票や耐震診断書など)が必要になるケースがあります。
事前に準備しておけばスムーズに申告が行えるため、不安があれば早めに税理士へ相談しておくと安心です。
マンションを生前贈与と相続ではどちらが得か?
マンションを親から引き継ぐ場合、「生前贈与」と「相続」のどちらが得かはケースによって異なります。
生前贈与では贈与税がかかる一方で、相続であれば基礎控除や各種特例が使えるため、一般的には相続のほうが税負担を抑えやすい傾向にあります。
ただし、生前贈与には「贈与時点での価格で評価される」「将来的な資産上昇リスクを避けられる」などのメリットもあります。
一方で相続では、居住用特例や取得費加算の特例が使えるなどの節税策もあるため、資産状況や時期に応じて最適な方法を選ぶことが重要です。
まとめ
相続したマンションを売却するには、相続登記や相続税の申告、売買契約や引渡しといった多くの工程を踏む必要があり、それぞれに専門的な知識が求められます。
手続きを誤ると、相続人間のトラブルや税務上の不利益が生じることもあるため、初めての方にとっては不安が大きいのが実情です。
だからこそ、正しい情報をもとに一つずつ丁寧に対応していくことが重要です。
また、譲渡所得税などの税負担が発生する可能性もありますが、「居住用財産の特別控除」や「取得費加算の特例」など、要件を満たせば節税できる制度も複数用意されています。
このような制度を上手に活用するには、早い段階での計画と専門家のサポートが不可欠です。
不安な点は専門家に相談しながら進めることで、ご家族の大切な資産を円滑に、かつ有利に手放すことができるでしょう。